時代の転換期に、アートは?
スクール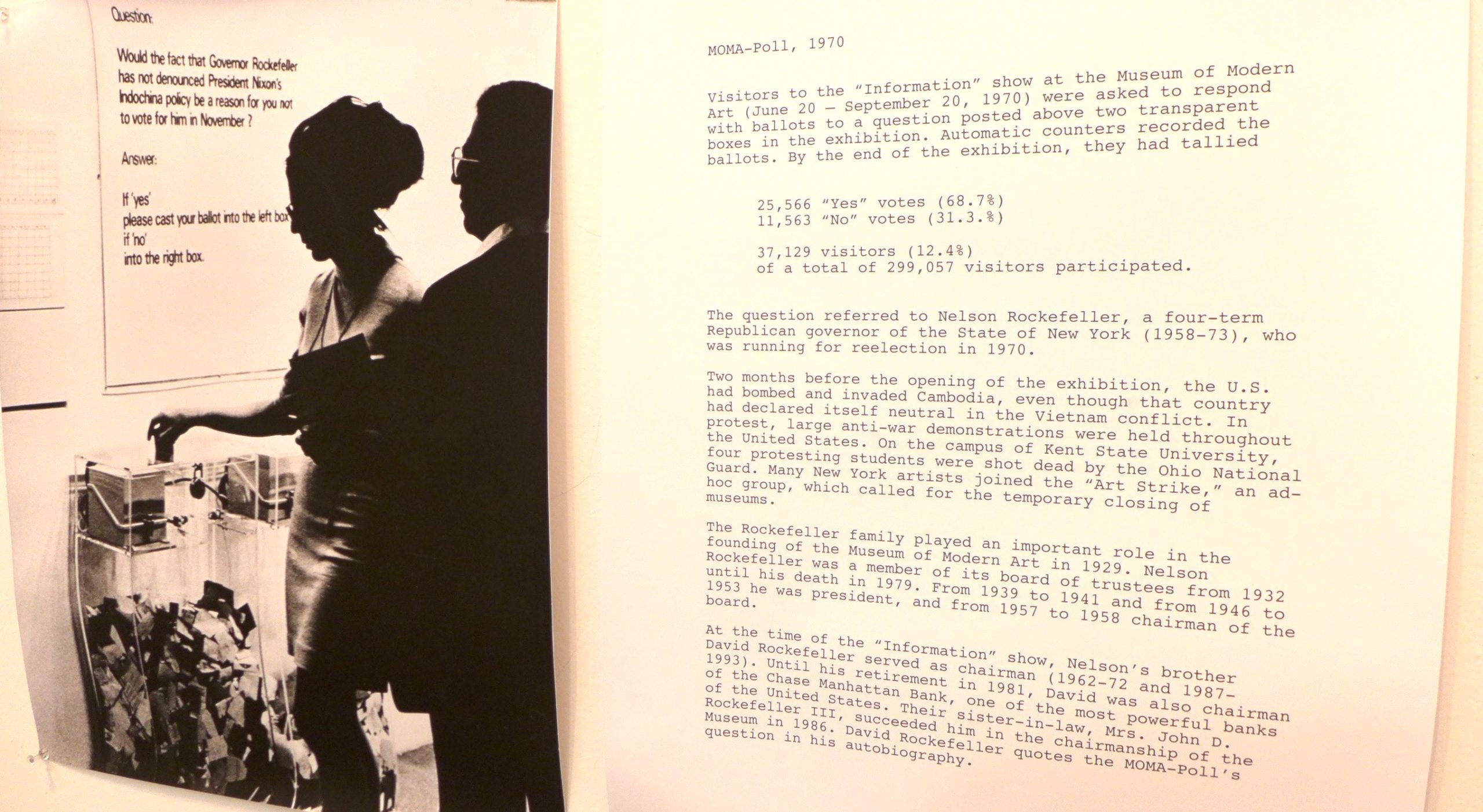
「仮説的」絵画とマイクロポップ−2000年代の絵画における一側面
9月13日(土)13:00 – 15:00
講師:桝田 倫広
2009年にラファエル・ルビンスタインによって書かれたエッセイ「仮設的な絵画」を紐解きながら、2000年代以降の絵画のある傾向を紐解きます。「仮設的な絵画」とは、モダニズムの美学に照らせば未完成や失敗作のように見える絵画のあり方を指します。こうした作品の背後にはどのような思考や態度、戦略があるのでしょうか。日本の2000年代の絵画の動向「マイクロポップ」にも接続させながら、映像や写真など他の表現形式の間で生き延びる「絵画」のあり方について考えを深めます。
ゲームから読み直すシュルレアリスム
9月20日(土)16:00 – 18:00
講師:中尾 拓哉
シュルレアリストの「遊び」から芸術とはなにかを考えます。シュルレアリスムは「超現実」といわれますが、実はその世界は私たちの現実と連続しています。彼らは時に、その現実にあるモノを選ぶことで作品化を試みますが、家や街の片隅に落ちているモノ、ファウンド・オブジェは、それを選んだ人のなにを語るのでしょうか。そしてその芸術性とは。『シュルレアリスム宣言』の著者であるアンドレ・ブルトンの考えをたよりに、モノによって繰り広げられる遊びとそこから見える世界の姿について考えます。
フルクサスと不可能なゲーム
10月4日(土)16:00 – 18:00
講師:中尾 拓哉
1960年代前半のニューヨークにおいてジョージ・マチューナスがはじめ、日本を含む世界各地で展開された前衛芸術運動、フルクサス。芸術だけではなく、音楽や詩などの領域を横断しつつ、日常と芸術を分けず、むしろ日常を芸術化する活動において、アーティストたちが構想するゲームの芸術性を考察します。誰もが関わることができるけれども、いつの間にか目的や戦いから逸れてしまうゲームについて、同時代との関係から読み解きます。
表現の自由はどこに−個が光る大正時代の芸術
11月1日(土)16:00 – 18:00
講師:小澤 慶介
日本において近代社会が形づくられ、個人が自由に表現できるようになっとき、表現者はその時代のなにをどのようなしかたで表したのでしょうか。都市と地方が形成され、関東大震災が起こり、権力による検閲がなされ、海外の革命や芸術運動を受けた激動の時代。小川芋銭や竹久夢二、村山知義といった芸術家をはじめ、江戸川乱歩や宮沢賢治などの文筆家、今和次郎などの建築家の実践に触れながら、同時代の社会と芸術の関係を読み解きます。
